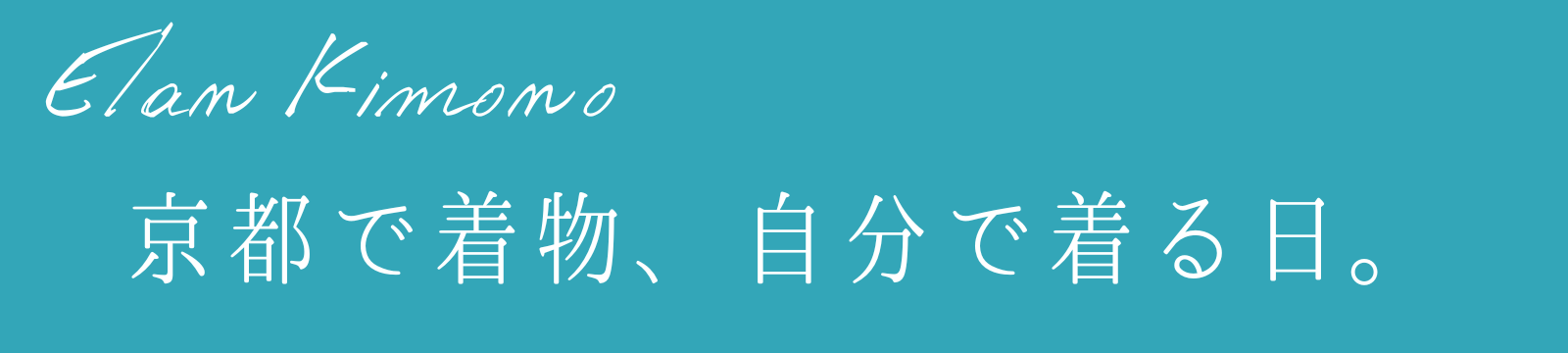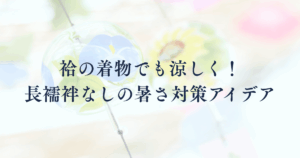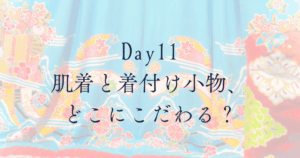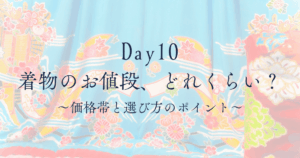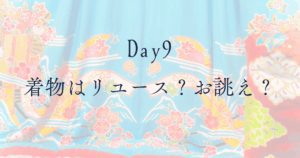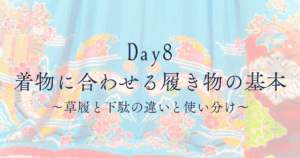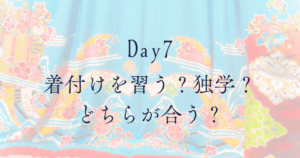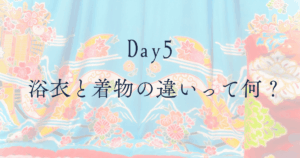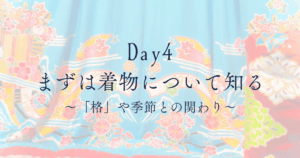「浴衣を着るための小物があれば、着物も着られるのでは?」
私もかつて、そう思っていました。しかし、実際に着物を着付けてもらおうとしたとき、浴衣用の小物では足りないものがあることに気づかされました。
今日は、浴衣と着物で異なる「着付け小物」について、体験を交えてお話しします。
目次
浴衣に必要なもの
浴衣の場合、必要なものは比較的少なく、気軽に装うことができます。
- 浴衣本体
- 兵児帯または半幅帯
- 肌着(ワンピースタイプが便利)
- 帯板(あればきれいに整います)
- 下駄
あとは、好みによって帯締めなどを合わせれば、十分に装いが整います。
私自身、初めて浴衣を着たときには、百貨店で揃えてもらった華やかな帯と帯締め、そして下駄で十分満足していました。
着物にはもう少し“支え”が必要
ところが、着物となるともう少しプラスされます。
浴衣のときに使っていた肌着や帯板は流用できますが、それだけでは足りないのです。着物の着付けには、以下のような物が必要になります。
- 長襦袢(襟元を整えるために欠かせません)
- 衿芯(半衿をきれいに見せるため)
- 伊達締め(長襦袢や着物を固定します)
- 腰ひも(少なくとも2〜3本)
- 足袋(実はいろんなタイプがあります)
- 帯枕(お太鼓などの形を作る際に使用)
- 帯揚げ・帯締め(フォーマル感を整える役割)
浴衣と同じ感覚で「着付けグッズは持っているから大丈夫」と思っていた私は、「衿芯?帯枕?なにそれ〜?!」と戸惑ってしまいました。
まとめ
同じ「和装」であっても、浴衣と着物では、求められる装いの完成度が異なります。こうした違いを一つひとつ理解し、揃えていく過程そのものが、着物との距離を少しずつ縮めてくれるように思います。
焦らなくても大丈夫です。着物に触れていくうちにわかります。昔はみんな着物を着ていたのですからね。