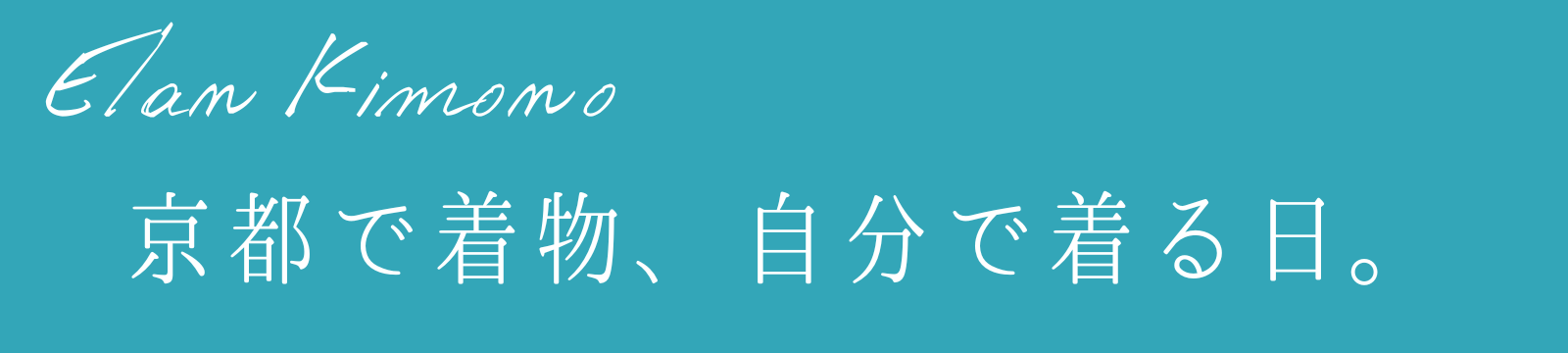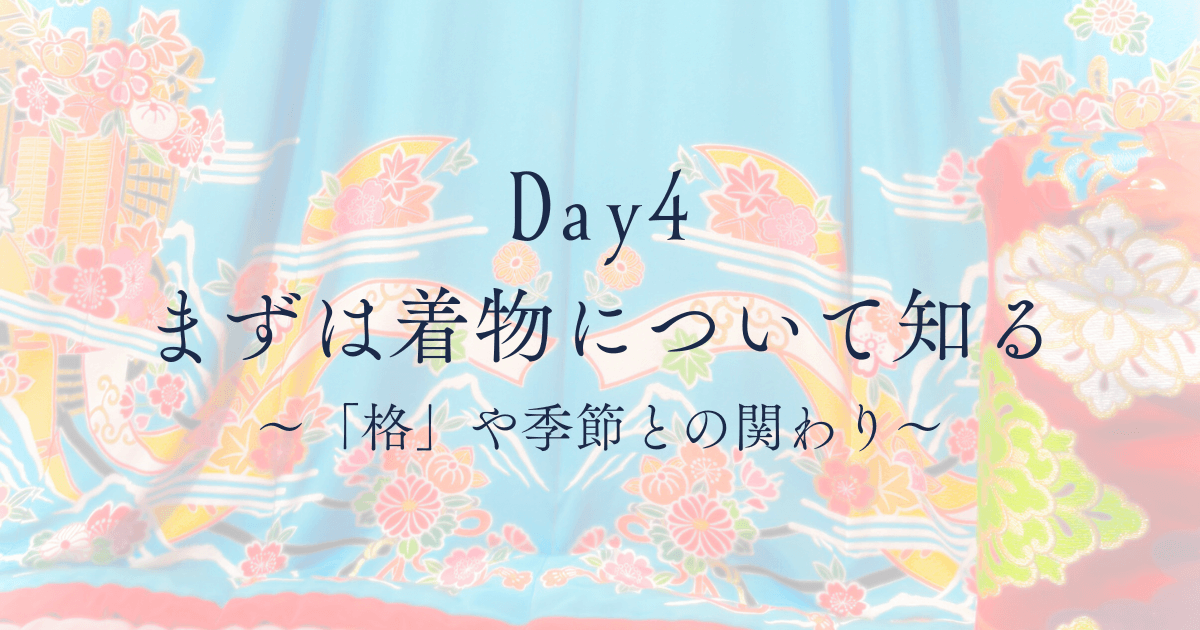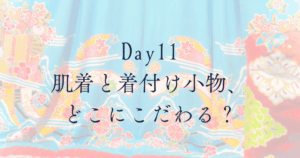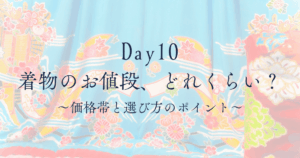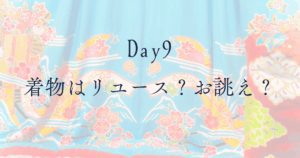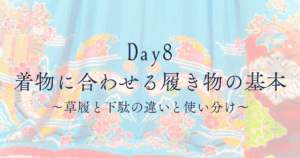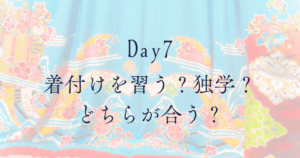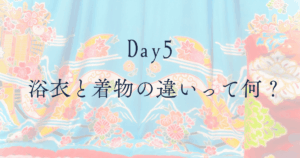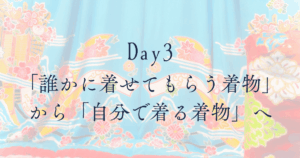着物を着てみたいと思い始めた頃、まず気になったのが「格」や「季節による違い」でした。
着物に対する熱が上がり始めていた私は、日々いろんな書籍やYoutubeなどをとにかくたくさん目にしていました。
すると洋服とは異なる魅力や美しい理屈が見えてきて、興味が深まっていきました。
今回は、そうした「着物の基本的な考え方」について触れてみたいと思います。
洋服との違い:袖ではなく「生地」で季節を表す
洋服の場合、半袖や長袖といった袖の長さで季節感を出すのが一般的ですが、着物では基本的に「裄(ゆき)」の長さは通年変わりません。裄とは、首の後ろの付け根から肩を通り、手首までの長さを指します。
では、どこで季節感を表すのかというと、それは「生地の素材」や「裏地の有無」によるのです。
袷(あわせ) … 裏地付き。10月から5月に着用されます。
単衣(ひとえ) … 裏地なし。6月と9月など、季節の変わり目に。
薄物(うすもの) … 絽(ろ)や紗(しゃ)といった透ける素材で、盛夏(7月、8月)に着用します。
素材の風合いや見た目の涼やかさで季節を映し出す――この繊細な感覚こそ、着物の美しさだと感じました。
ちなみに最近では、多くの方が厳格にこのルールを守るべき、という考えではなくなってきているようです。
近年は真夏日や猛暑日が増えてきている影響もあり、上記の季節感はおおまかな目安として、気温や体感に合わせて先取りしたり、逆に長めに着ていても良いと考える方が多いようです。
「格」とは、場にふさわしい着物選びの考え方
着物には「格(かく)」という概念があります。これは、洋服にたとえるならばカジュアルなワンピースとフォーマルなドレスの違いのようなもの。着物も、目的や場面に応じてふさわしい種類を選ぶことが求められます。
以下の表に、基本的な「格」の種類と用途をまとめました。
| 格の名称 | 主な用途 | 着物の例 |
|---|---|---|
| 正礼装 | 結婚式・式典など | 黒留袖、色留袖、振袖、訪問着(紋付き) |
| 準礼装 | 入卒式・お祝い事 | 訪問着、付け下げ、色無地 |
| 普段着 | お稽古・街歩きなど | 小紋、木綿着物、紬、ウールなど |
私が学んだのは、「主役がだれか」という視点が大事であるということです。誰かの結婚式や子供の行事に出席する場合には、上記のような格や季節感を守るのがベストでしょう。
初心者にもわかりやすかった書籍と動画
書籍
まずはこれ1冊でOK!超初心者さんから、コーディネートに悩む中級者さんまでにおすすめできる1冊をご紹介します。
季節感や見本となるコーディネート、そして着物の柄に関する知識や着付けはもちろん、着物を着ている時のマナーまで掲載されており見応えのある書籍です。
Youtube
一級着付け講師のすなお先生が、明るくやさしく丁寧に解説してくださいます。トピックスが豊富なので、着物のことでわからないことがあればまずすなお先生の動画を検索してみるとよいです。
毎日着物生活の女将・木下紅子さんが着物の着かたやライフスタイルに取り入れるヒントを配信されています。鏡に向かい合うスタイルなので、正面だけでなく後ろ姿も見ることができ、見ながら着る際にわかりやすいです。毎日着物生活をされていて私の憧れのスタイルです。
まとめ
着物について知っていくにつれて、洋服とは異なる文化の中で育まれてきた装いだなとよく感じるようになりました。最初は戸惑うこともありますが、その理屈や美意識を理解することで、一歩ずつ着物との距離が縮まっていくように思います。